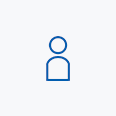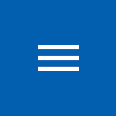個の集まり “ワンチーム”へコロナ禍を乗り越えた結束力
昨年10月20日~23日に大阪・ヤンマーフィールド長居で開催された「第97回関西学生陸上競技対校選手権大会」(関西インカレ)で、びわこ成蹊スポーツ大学陸上競技部が男子フィールドの部優勝(57・5点)、男子1部総合3位(88・5点)と、ともに過去最高順位となる快挙を成し遂げた。新型コロナウイルスの感染拡大で満足な練習ができず、大会も5月から10月に延期されたうえ無観客で開催されるなど、過去にない苦難を乗り越えての大躍進は、理不尽な状況下でも目の前の目標に向かってひたむきな努力を続けることの大切さを私たちに伝えてくれた。
予期せぬ事態に見舞われたからこそ、自己研鑽を積めたのかもしれない
長く陸上部を指導してきた渋谷俊浩部長が「先行きが不透明な状態がこれだけ長く続いた経験は、競技生活45年以上になる私にとっても初めてのことでした。厳しい状況下でも何とかしようとしている選手たちに力をもらいながら、選手たちの『陸上をやりたい!』という大きなエネルギーが正しい方向を向くよう努めました」と語るように、昨年の同大会で過去最高のポイントをあげた陸上部もまた、他の部活動と同様に、新型コロナウイルスの感染拡大という予期せぬ事態に苦しみ続けた。
部活動の自粛、5月に開催される予定だった関西インカレの延期……。世界的なパンデミックの広がりとともに予想外のことばかりが起こるなか、陸上部員たちはSNSを駆使してチーム全体、それぞれのパート間、選手個人間でコミュニケーションをとりあって自主練習に励み、モチベーションを維持していった。
昨年の大会はメンバーに選ばれず、本紙のカメラ担当として先輩や仲間たちの活躍を撮影した難波隆輝選手(4年次生)は「ラストチャンスの今年こそ、出場したかった関西インカレの延期が決まったときは、大きな目標が消えて戸惑いました。それからは自主的にコツコツやろうと思ったというより、陸上部員全員がコツコツせざるをえない状況に追い込まれました。でも、そうした過程で僕自身も一人でじっくり陸上競技と向き合えたからこそ、入学以来取り組んでいた十種競技から走り幅跳びに種目を絞って最後のチャンスにかける決断ができたのかもしれません」と振り返る。
学部生時代に十種競技の選手として陸上部を支え続けた黒田貴稔助手も「昨年のチームは飛び抜けた力のあるエース級の選手を中心に回っていました。今年は突出した選手はいませんが、地道な努力をこつこつ積み上げていくタイプの選手が多くいました。コロナのような逆境に強い選手たちが集まった世代ともいえるかもしれません」と語るように、コロナ禍という予期せぬ事態に見舞われたからこそ、そうしたタイプの陸上部員たちは、これまで世代とは違う感覚で自己研鑽を積めたのかもしれない。
マネージャーとしてチームを支えた山本真子さん(4年次生)も「ひとつ上の先輩方はすごく期待された学年で、ひとつ下の学年も自分たちから発信していく部員たちが多いイメージなのですが、私たちの学年は静かに、影に隠れてひっそりと努力するようなタイプが多かった。でも、そんな選手たちだからこそ、それぞれが緊張感を持ってコロナ対策に注意をはらいながら、自分たちの個人練習にもしっかりと取り組んでくれたと思います」と、自らとともに成長してきた同学年の選手たちの特質について語る。
だが、自粛期間が終わり、大学のグラウンドを使用できるようになっても、以前と同じように全部員が集まる機会はなかった。学内で統一された人数制限の規定をしっかりと守りながら、各パートの練習や記録会の運営なども工夫したが、関西インカレに向けた不安は拭えなかった。
「可能な範囲で強化は進めてきましたが、試合経験不足は明らかで、ふたを開けてみなければわからない状況でした」と、渋谷部長は振り返る。
そして「仲間の声援もなく、いつもの大会とはまったく違う雰囲気」(山本マネージャー)のなかで迎えた本番。チームに流れを呼び込んだのは、大会初日の第一種目として行われた十種競技の100mに出場したキャプテンの遠山裕介選手(4年次生)だった。大会直前のけがをして出場した遠山選手は、11秒49のタイムで5位につけたのだ。
関西インカレは各パート間の結束が、チームとしての総合力として結果に出る
渋谷部長が「遠山選手本人はもちろん、チーム全体が波に乗ることができた大きな要因だった」と分析するように、その後も三段跳びで楠本政明選手(4年次生)が15㍍87㌢を跳んで優勝したのをはじめ、走り幅跳びに専念した難波選手も7㍍31㌢と、自己記録を大きく更新して3位に入る大健闘を見せた。
だが、そうした個の力だけでは、今回のような結果を手にすることができないのも陸上競技の本質である。
黒田助手が快挙の原動力としてあげたのは、チームとしての団結力だ。
「関西インカレは総合力が問われる大会です。各パート間の結束が、チームとしての総合力として結果に出ます。『他パートが失敗したとしても自分たちがカバーし合おう』という意識は、普段から共有していないと本番で発揮できません。僕が1年次生や2年次生の頃はパート間での繋がりが薄く、みんなでがんばろうという意識が薄かった。みんなで強くなっていこうという意思を部員たちで共有できたことが、今回の結果をもたらした要因だと思います」
今大会で総合1位の座に就いた関西学院大や2位の立命館大のように、高校時代に全国のトップレベルで戦った選手はほとんどいない。そんな大学が総合3位、長く大阪体育大が覇権を独占してきたフィールド部門で優勝した快挙は、学外の陸上関係者たちからも驚嘆の目で見られているという。
個人種目の集まりから〝ワンチーム〟に成長したびわスポ大陸上部は今後、どこまで飛躍し続けるのだろうか。
就任して以来、常に過去最高の成績を更新し続ける石井田茂夫監督は「コロナの影響で練習ができない期間があっても、各コーチが選手とうまくコミュニケーションをとって、いつでも練習に戻れる状態を作ってくれました。個の力、主体性をもって学生たちに陸上に取り組んでもらうには、組織の力も必要。そのことを実感したシーズンでした。新チームはスタートからコロナと向き合うことになりましたが、これからも学生たちを信じてがんばっていきたい」と話している。(文責・安田ひかり)
-
特色あるびわこ成蹊スポーツ大学の教育
研究活動について
教育・研究を支える機関
-
高大連携
![びわこ成蹊スポーツ大学 [OSAKA SEIKEI UNIVERSITY]](/common/img/header_img_logo.png)